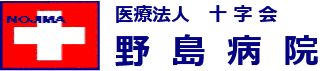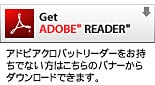薬の正しい使い方
薬を正しく使っていただくために
ここは、薬を正しく理解し使用していただく為のコーナーです。
お薬について知っておきたい知識
薬は何のために飲むのでしょうか?
薬は理由もなく飲むものではなく、ケガや病気そのものを治療したり、症状を和らげたりするために使われます。また、発病を抑えたり、発病しても症状が軽くすむように予防的に使われる薬もあります。
薬のほとんどは本来、体にはないもので、勝手な使い方をすれば有害な作用や中毒を招いてしまいます。
患者さまに渡された薬は、患者さまの現在の病気に対して処方されたもので、治療の効果が得られるようにと考えられています。
人は、年齢・性別・体重・身長・体調・病状など、一人として同じ条件の人はなく、同じ病気、同じ薬であっても使い方も同じとは限りません。ですから自分の判断で勝手に飲むことをやめたり、増やしたり、他人にあげたり、別の病気に使ったりしないようにしましょう。
服用中に何かいつもと違うと感じたり、他の薬を併用するときは必ず主治医または薬剤師にご相談ください。
薬の保管は、湿気、高温、直射日光を避け、子供さんの手の届かないところに保管しましょう。
薬は理由もなく飲むものではなく、ケガや病気そのものを治療したり、症状を和らげたりするために使われます。また、発病を抑えたり、発病しても症状が軽くすむように予防的に使われる薬もあります。
薬のほとんどは本来、体にはないもので、勝手な使い方をすれば有害な作用や中毒を招いてしまいます。
患者さまに渡された薬は、患者さまの現在の病気に対して処方されたもので、治療の効果が得られるようにと考えられています。
人は、年齢・性別・体重・身長・体調・病状など、一人として同じ条件の人はなく、同じ病気、同じ薬であっても使い方も同じとは限りません。ですから自分の判断で勝手に飲むことをやめたり、増やしたり、他人にあげたり、別の病気に使ったりしないようにしましょう。
服用中に何かいつもと違うと感じたり、他の薬を併用するときは必ず主治医または薬剤師にご相談ください。
薬の保管は、湿気、高温、直射日光を避け、子供さんの手の届かないところに保管しましょう。
薬の服用は指示のとおりに
高熱の場合や痛みの激しいときなどその時だけに服用するものを頓服薬といい、これはたとえば1回1錠、 3回分というように指示され、その症状のあるときのみ服用します。
薬の袋には、「1日3回、1回につき2錠を食後服用」といったように量や飲み方の指示がされています。 これは薬の効果が十分にあらわれ、副作用が現れなくてすむように考えられているからです。
薬が効果をあらわす時間は、薬の種類や剤形、量によって違います。数時間のものから24時間も効いているものもあります。
一般に、薬は十分な量の水かぬるま湯で飲むように指示されています。水を用いずにそのまま薬を飲むと、 薬が溶けにくくなり、食道にへばりついて、そこに悪影響を及ぼしたり、胃に強い負担をかけることになってしまいます。
また、それ以外のもので飲むと、さまざまな影響が出てしまうことがあります。
薬の袋には、「1日3回、1回につき2錠を食後服用」といったように量や飲み方の指示がされています。 これは薬の効果が十分にあらわれ、副作用が現れなくてすむように考えられているからです。
薬が効果をあらわす時間は、薬の種類や剤形、量によって違います。数時間のものから24時間も効いているものもあります。
一般に、薬は十分な量の水かぬるま湯で飲むように指示されています。水を用いずにそのまま薬を飲むと、 薬が溶けにくくなり、食道にへばりついて、そこに悪影響を及ぼしたり、胃に強い負担をかけることになってしまいます。
また、それ以外のもので飲むと、さまざまな影響が出てしまうことがあります。
薬の服用時間の目安について
●食前 |
胃の中に食べ物が入っていないときです。 食事をするおよそ15分〜30分前です。食欲増進剤や、吐き気止め、胃潰瘍 などの薬は食前に服用する場合が多いです。 |
●食直前 |
食事を始めるすぐ前です。 今は胃の中がからっぽですが胃の中の食べ物が薬の効果に重要である場合です。 血糖を下げる薬で食事後に血糖が急に上がるのを抑えるとき指示されます。 |
●食直後服用 |
食事を終えてすぐ服用してください。 鎮痛剤、鉄剤などで胃への負担が大きい時、こうした指示がなされます。 |
●食後 |
胃の中に食べ物が入っているときです。 食事をしてからおよそ15分〜30分後。 胃の中に食べ物があり、薬による胃への刺激が少なくなります。 |
|
●食間 |
食事と食事の間のことです。 例えば、朝食と昼食の間。食事の後約2時間くらいして服用してください。 食事中に服用することではありません。 一部の抗菌剤や漢方薬のように食事により影響を受ける薬で指示されます。 |
※ 上記の時間はあくまでも目安です。食事により薬の働きに影 響が出るのは確かなことですが、
一方では飲み忘れるよりは時間を少しずらしてでも服用した方がよいという考え方もあります。
その人その人の生活(食事)パターンにあっていて、薬も十分に働くような飲み方を、医師や
薬剤師とよく話し合ってみましょう。
小児、妊婦、授乳婦、高齢者に対する注意
身体的な面で影響をもっとも受けやすい小児や高齢者への薬の投与は慎重に行わなければなりません。では、どのような注意が必要なのでしょうか。
▲小児の場合▲
小児は生体機能が未発達のため、薬の負担がかかる肝臓や腎臓の働きも十分ではありません。そのため薬の投与は、年齢や体重、あるいは体表面積に応じて用量が決められています。
▲妊婦の場合▲
妊娠中の母体はいろいろなホルモンの影響で、薬による副作用があらわれやすいのですが、糖 尿病や甲状腺機能異常などの病気にかかっておられる場合は適切な治療が必要です。特に、勝手な自己判断による薬の服用は、胎児の発育に影響をおよぼすこと もありますので、産婦人科の医師または薬剤師にご相談ください。
▲授乳婦の場合▲
母親が薬を服用すると、多くの薬が血液を通して母乳に移ります、そのため、授乳によって、新生児や乳児などへの影響が考えられるため、薬を服用する際には産婦人科の医師または薬剤師にご相談ください。
▲高齢者の場合▲
お年寄りの方は、血圧の薬や心臓の薬など、薬を併せて使用することが多くなります。使用期間も長くなりがちです。 また、年とともにどうしても肝臓、腎臓などの働きが弱くなっています。 またホルモンなどの分泌機能が弱まり、投与した薬の効果にも変化があります。 このような高齢者における薬の効果には個人差が大きく出ますが、一般的に高齢者に薬を用いる場合、成人より少なくしてあります。
薬の保管
冷蔵庫に入れる、光の当たらない場所に置く、湿気に注意するなど、薬の決められた保管方法は、その効きめを保つ上で重要な事項です。その注意点を見ていきましょう。
▲乳幼児・小児の手が届かない所に保管しましょう▲
最もこわいのは乳児・小児の誤飲です。そのおそれのある場所に薬を放置しないように注意しましょう。不要の薬は子供の目に触れないように処分することが大切です。
▲湿気、日光、高温をさけて保管しましょう▲
薬は湿気、光、熱によって影響を受けやすい物です。密閉できる容器に薬袋ごと入れ、直射日光があたらず、暖房器具から離れた場所に保管しましょう。
▲薬以外のものと区別して保管しましょう▲
誤用を避けるために、飲み薬とぬり薬は区別して保管しましょう。 また農薬、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管しないようにお気をつけください。
▲他の容器へのいれかえはやめましょう▲
薬を使い古しの他の容器に入れかえると、内容や使い方がわからなくなり誤用や事故のもとになりますので、ご注意ください。
▲古い薬の使用はやめましょう▲
保存条件・時間によって薬は変質します。古い薬や変質した様な外観に異常がみられる薬については、使用前に医師、薬剤師にご相談ください。